
2014 年3月13日、東京目黒雅叙園にて開催の「データマネジメント2014(http://www.seminar-reg.jp/jdmc/dm2014/)」のユーザセッションからいくつかをご紹介します。
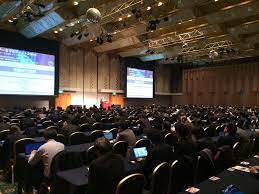

Contents
- エンタープライズHubを中核にした先進アーキテクチャの実像システムの疎結合化、可視化とデータの利活用
(協和発酵キリン) - 新しい消費者理解から始まる新しいデータマーケティング
〜データドリブンな企業になるための考え方と実践〜
(トランスコスモス・アナリティクス) - “算数”から“数学”へ、がデータ活用の真髄
情報系のデータ・ハブを目指したDICの取り組み
(DIC) - ネットストアにおける「お客様と時間を共有する」CRM戦略
〜MUJI Digital Marketingの展望〜
(良品計画) - 変化対応力を10年以上維持する情報アーキテクチャ
DBの明確な分離や運用体制が鍵
(JFEシステムズ) - データ分析の第一人者が語る
普通の企業における専門家や専門組織のやりがいと苦労
(大阪ガス) - 食べたい寿司をタイムリーに
”スシロー流データ活用術”
(あきんどスシロー) - 情報系システムアーキテクチャ策定の
ベストプラクティス
(みずほ銀行) - 顧客満足を生み出し、業績貢献する仮説思考に基づくDBマーケティング
(オイシックス) - ビッグデータ時代のBIシステム構築
開発標準化の取組みと活用事例について
(カゴメ)
エンタープライズHubを中核にした先進アーキテクチャの実像システムの疎結合化、可視化とデータの利活用

協和発酵キリン株式会社
情報システム部長
篠田 敏幸 氏
クラウド時代の理想形と呼ぶべき情報システムアーキテクチャを体現
協和発酵キリンは、がん・腎・免疫疾患などを対象とする医療用医薬品の製造・販売を柱にグローバル規模で事業を展開している。
同社のビジネスを支える情報システム群は現在、2つのデータベースが中心に配置され、各システムがそれらを介して連携動作するシステムアーキテクチャへと発展している。2つのデータベースとは、各種のマスターを一元化した「マスターHUB」、トランザクション・データを集約した「トランザクションHUB」を示す。これらのHUBを介在させることにより、パッケージ等の周辺処理コンポーネントはその時点で最適なものに取り替えることができる。
トランザクションHUBは、異システムのバッファーとして機能し、運用管理負荷を軽減するのに役立っている。一方、各システムで共通利用するマスターは、マスターHUB上でその正本が一元管理されている。この正本をオンプレミス、クラウドを問わず各システムと同期することでトランザクションの品質を担保している。
「データ中心の考え方が当社に根付いた時期は、1980年代のホストコンピュータ時代に遡ります。経営統合などの企業環境の変化、実装する技術やツールの進化に対応しながらも、ベースとなる考え方はその後も貫かれました」と篠田氏は説明した。
同社の情報システム部門(社員50名)の中には、データ管理を専門とする2名の担当者で構成されたチームがある。このデータ管理チームこそが、コンテンツ整備とデータ資源管理ツール(eリポジトリ)構築の担い手である。コンテンツ整備では、開発・保守経験者などの有識者を対象にナレッジ・ノウハウの収集・整備を行い、作業手順の標準化を進めている。
他方、データの資源管理については、もともと同社は1982年のホストコンピュータ時代からIRMリポジトリを導入して以来、整備・運用を行ってきた歴史がある。eリポジトリは、それら既存リポジトリをコンバートして2012年に運用が開始された。eリポジトリのユーザインタフェース(UI)には、インターネット辞書のwikipediaなどで馴染み深い画面が採用されている。システム、ドメイン、データ、エンティティ間の関連などは次々とリンクを辿ることで理解が進む仕掛けである。メタデータについても、概念モデルをベースにeリポジトリで論理定義されている。
データ管理チームでは、上述のコンテンツ整備とデータ資源管理ツールを組み合わせて、データ資源整備と可視化されたコンテンツの継続的な改善を行っている。
2013年には、全システム部員を巻き込んで共通マスター構造の見直しと、古くなったマスターデータの物理的な削除を行った。修正したデータ項目は146項目、削減したマスターデータは全体の20.9%に達した。eリポジトリの導入により、データ資源見直しに係る保守人材の育成期間が短縮し、整備のスピードアップが図られている。
「データ資源管理作業には費用をかける価値があります。ただ、試行錯誤を重ねる中で情報基盤のアーキテクチャは、ほかでもない自社の社員が真剣に考えるべきであり、管理は自らの手で継続させることが命である、という教訓を得ました。今後もデータの整備を継続するとともに、eリポジトリの外部提供、業務視点で見たナレッジ・ノウハウも含めてシステムに関するすべての情報を連携させていきたいと考えています」と篠田氏は意気込みを述べた。
(まとめ:大倉愛子)
新しい消費者理解から始まる新しいデータマーケティング
〜データドリブンな企業になるための考え方と実践〜

トランスコスモス・アナリティクス株式会社
取締役副社長
萩原 雅之 氏
多角的なデータから心理を読み解き、イノベーションのきっかけをつかむ
1980年代半ばから30年にわたってマーケティングリサーチ業界に身を置いてきた萩原氏は、90年代まで消費者の声を拾う市場調査の手法は、アンケートやグループインタビューが主体だったが、昨今は、デジタル化された多種多様なデータを入手可能となっていると振り返った。こうした「ビッグデータ」をマーケティングに役立てようとする機運も高まっている。
「とはいえ、この間にマーケティングリサーチの考え方も変わってきています。単純に従来の延長線上でデータを分析しても期待した成果を得られないでしょう」と注意を促した。
萩原氏がまず指摘したのは、マーケット定義の難しさだ。市場間の競争激化が背景にある。顧客は新たに創造された市場へ移っている。したがってライバルには同業種だけでなく、他の市場でパイを広げる異業種が含まれる。同業他社との戦いにのみに目を奪われていると、縮小する市場に取り残されてしまう。その意味で、既存市場におけるシェア占有率の高さ自体の価値は薄れつつあると萩原氏。「同業種との間で市場シェアを奪い合う従来の戦争型マーケティングではなく、顧客の心の中のシェアをどれだけ自社ブランドで占めるかがより重要となっています」と説明した。
このような“恋愛型の戦争”下では、集団としての顧客像、あるいは最大公約数的な特性をそこから切り取る断片的なリサーチよりも、パーソナルな顧客の心理をより深く理解し、そこから企業がインサイト(気づき)を得る包括的なデータ収集・分析・活用がいっそう重要となる。
ネット広告は、そうした取り組みが進む領域のひとつだ。あるウェブ媒体にアクセスする読者の閲覧履歴から、特定の読者がダイエットのページを高い頻度で見ていることがわかったとしよう。さらに、その読者がスマフォにダウンロードしたアプリでランニングの距離を計測したり、愛犬との散歩をSNSに紹介したりしていることが、SNSやアプリに登録したIDやメールアカウントから把握されたとする。このようなデジタルフットプリントを用いることで、より鮮明な消費者像が浮き彫りになる。
こうした顧客情報は、広告枠を提供するメディアと広告主をマッチングに活用されている。膨大なデータを素早く分析し、最適な広告を最適な媒体に打ち出すことを目的とするDMP(Data Management Platform)が急速に台頭しているのはその現れだ。広告枠の値段は需給に応じて変動し、入札によって売買が成立する。広告枠を広告代理店などの営業担当者が人海戦術で販売していた時代とはすっかり様相が異なる。
「ただし、機械学習による予測と最適化だけではマーケティングの効果は次第に逓減し、いずれ頭打ちになります。さらなるビジネスの成長を遂げるには、ある種の飛躍、ひらめきが必須。未来を予測するのではなく、未来を作ることが重要です。そしてまた、イノベーションを起こすためにも顧客行動の深い理解が欠かせません。ビッグデータを用いた顧客理解は、データサイエンスに基づく顧客行動の予測と対応の最適化のためだけでなく、未来を変えるイノベーションのインサイトを得るためにも不可欠です」と萩原氏は語った。
(まとめ:柏崎吉一)
“算数”から“数学”へ、がデータ活用の真髄
情報系のデータ・ハブを目指したDICの取り組み

DIC株式会社
システム本部
本部長
小田 滋 氏
分析で得られた確率やモデルの精度を高め、経営に資する仕組みを社内に造る
DIC(ディーアイシー)におけるビジネスのコア領域は、創業期から続くインキ事業だ。培った技術を基盤に多角化を進めてきたことで、ポリマ、ファインケミカル、アプリケーションマテリアルズといった領域でも世界トップシェアの製品を多数有する。世界61の国と地域に176の関係会社を展開するグローバルカンパニーとして知られている。
講演者の小田氏は、1990年に同社原料部門で国際調達の組織立ち上げと購買情報のDWH構築に携わった。2001年からは情報システム部門で情報システム基盤の拡充に努めてきた。その頃から事業領域の拡大と業績管理手法の変更、化学物質の輸出入や環境保護に関する国際的な法規制/コンプライアンス対応強化を背景に、基幹系システムの再構築と情報系データの一元管理が、同部門の大きなミッションとなっていた。
2004年 6月、当時としては大規模な2TBストレージを全社のデータ・ハブとして導入し、社内におけるデータベースの共用化を促した。翌年から欧米を皮切りにSAPを導入。2007年5月には日本のホストシステムのEDP会計データベースを社員に公開し、社内における情報活用を後押しした。
2009年2月には、化学物質情報総合管理システム「CIRIUS」を稼働させた。化学メーカーなどに公表が義務づけられているMSDS(化学物質等安全データシート)をこれにより、1時間あたり2000件、自動生成する仕組みを実現した。2014年2月には「CIRIUS」のDBをIAからSYSTEM zに移行することを決定、来年1月の本稼働を見込んでいる。
MSDSの件数は現在およそ390万件、データ量にして約900GBに達する。従来は、製品含有物に係る法規制の検索に1時間以上要することもあった。しかし現在は1〜2秒程度と格段に速くなった。10カ国の法規制にあわせて書き分ける文書も一度に同時生成できるようになった。このために、完全に正規化した2列のカラム指向型DBを用いている。
「取引先の拡大、規制物質の増加などへの確実な対応に耐える必要がありました。データ構造と処理の仕組みを吟味した結果、正規化したデータに基づくDOAをシステム化の方針に据えました。あらゆるデータを先に構造化してからDBに登録しています。データの利用目的が明確であれば、この仕組みで高いレスポンスと拡張性が得られます」と小田氏は説明した。
とはいえ、これまでの情報システムは、演算やデータ処理における正確性や迅速性が重視されるものだった。適用分野も決算・会計、財務報告などに代表される基幹系業務が主眼だった。
「今後IS部門が果たす役割の一つは、中期経営計画にも示しているように、グローバル規模で経営に資する仕組みを社内に造ることです。数学を駆使した確率統計モデルの構築とシミュレーションなど、未来を見据えたビッグデータの活用がさらに重要になるでしょう。BI担当を含めて、データに携わる社員は海外も含めて10数名。ITをより活用し、経営を支援してまいります」と結んだ。
(まとめ:大倉愛子)
ネットストアにおける「お客様と時間を共有する」CRM戦略
〜MUJI Digital Marketingの展望〜

株式会社良品計画
WEB事業部長
奥谷 孝司 氏
マーケティング効果の測定精度を高めて顧客との関係強化を促進
「無印良品」ブランドで知られる良品計画では、全国各地の店舗、およびネットストアを通じて商品を提供している。奥谷氏が所属するWEB事業部でも、ソーシャルメディアやメールマーケティングなどを駆使した様々な施策を講じ、最大の顧客接点である店舗への送客に取り組んできた。「とはいえ、施策間の連携がまだ十分ではありませんでした」(奥谷氏)。
こうした中でWEB事業部が注目したのは、顧客の購買時間である。市場の数ある商品群の中で、顧客はなぜ同社の商品を選ぶのか、なぜこの店舗、ウェブサイトでショッピングするのか。購入時点だけでなく、購入前の検討、そして購入後の使用・消費の段階まで、情報収集のスコープを広げることにした。
そこで欠かせないのが、「MujiPassport」と呼ばれるモバイル端末向けのアプリだ。デジタルポイントカードとして、また、商品検索機能や特典情報などのニュースを配信する媒体(メディア)として顧客の持つスマフォ上で動作する。現在、このアプリを約140万人がダウンロードしている。
特にWEB事業部が重要視しているのが、チェックイン機能だ。買い物の支払い時や入店時に、MujiPassporのインストールされたスマフォを持つ顧客はマイル(ポイント)を貯められる。一方、同社の本部側では、顧客がどの店で何をショッピングをしたか、どの店舗によく足を運ぶのかなどの情報を把握できる。
同社にはすでに、MUJIカードを保有するカード会員(44万人)、ネットストア会員(434万人)、口コミ情報が集まるソーシャルレビューサイトのmyMUJI会員(37万人)を擁する。すべてに加入している顧客も存在するが、個別にまたは重複して加入・登録している顧客のほうが圧倒的に多い。したがって最新の会員情報を得られなければ、会員データベースの精度が低下し、分析結果が鈍る要因となる。来店時にカードを携行しなかったために、やむを得ず新規発行しているケースもある。MujiPassportをインストールしたスマフォであれば来店時に忘れにくく、本部側も会員情報に関する最新データをキャッチしやすい。各カテゴリの会員データを紐づけることも技術的には可能だ。ID-POSよりも廉価に、購買時間における顧客データを収集管理できる利点も手にした。
その結果、これまで30代の女性客中心だった同社の顧客層に加え、若年層への直接的なリーチが可能になった。また、マイル付与が誘因となり、週末を含めて売上が伸びることもデータからわかった。
ただ現場からは、「ビッグデータを分析するまでもなく、顧客の動きはすでにわかっていた」という声がほとんどだと奥谷氏は打ち明けた。いわば、「I Know Syndrome」だ。
「ビッグデータ分析は地味で、簡単に画期的な仮説や知見は生まれるわけではありません。しかし、多様なデータソースからこれまで見えにくかったお客様の行動が以前よりも明瞭になりつつあります。O2OなどのITを活用し、データの精度を高め、これまで難しかったマーケティングの効果測定の精度を高める必要があります。思い込みや施策の打ちっぱなしではなく、データに裏付けられたマーケティングを顧客とのさらなる関係強化に役立てたいと考えています」と奥谷氏は述べた。
注釈:なお会員数等の数値は講演当時のものです。
(まとめ:柏崎吉一)
変化対応力を10年以上維持する情報アーキテクチャ
DBの明確な分離や運用体制が鍵

JFEシステムズ株式会社
東京事業所
関連企業第1システム部
部長
森 弘之 氏
情報基盤を管理する専任組織がデータモデルを軸にシステムの設計開発を進める
2003年、日本鋼管(NKK)と川崎製鉄の2社の経営統合を経て、JFEスチールが誕生した。新たな事業体制を支える経営システム「J-Smile」の構築では、専門の情報基盤チームがデータを中心とする設計開発を進めてきた。情報基盤チームは、JFEスチール、情報システム子会社のJFEシステムズとエクサ、および他企業の有識者により結成された組織だ。
経営統合から3年後の2006年までに、販売、工場への製造指示、流通系などの基幹系システムがJ-smile上に再構築された。J-Smileはメインフレームを基盤とし、業務アプリケーションはJavaで開発されている。データベースとアプリケーションを明確に区分し、システム修正の容易さと品質向上を図っている。データ項目は9万件、容量にして10TBものボリュームに達した。
概念データモデルの策定は、経営統合に先立つ2002年後半から始まった。旧2社は共に旧システムが構築された時代からビジネスモデルが変化していることを認識していた。概念データモデルの策定では、このような変化したビジネスモデルに対応すべく、中核となる引合、注文、製造仕様、製品仕様などのエンティティを抽出・定義し、相互の関連づけおよびエンティティの状態遷移を各業務オーナーと共に検討を重ね、システムの骨格作りと完成イメージの共有化を図った。「業務プロセスの統合検討から開始していたならばもっと時間がかかっていただろう」と森氏は指摘した。
現在、このモデルに基づいて開発したシステムのエンティティ数は約7,000である。そのうち1,600を占める共有層は全体最適の視点で概念データモデルから継承された情報であり、システム全体で共有される。他の固有層は基本設計以降に設計されたもので、個々のAPで必要な情報であり、管理は各業務オーナーの裁量に任されている。ただし、個別アプリの開発チームが触れるJavaアプリケーションからはクラスに対応するDBのテーブルが直接見えない。SQLの作成は業務アプリケーション開発部門の要求に基づいて情報基盤チームが一元的に行うことでテーブルの乱立に歯止めをかけている。データ定義は、業務を熟知した担当者を専任とし、業務担当からの登録依頼に基づいて項目やコードを一元管理している。これによりデータの品質を担保し、業務部門、システム開発部門におけるデータ活用を促している。
業務アプリを個別に開発する場合、「データアクセスの申請からSQLを内在したデータアクセス部品のリリースまで1週間程度要しました。スピードを重視する現場からその時間に不満も出ましたが、結果的にワークフロー化して一貫性を保つ方が生産性や品質を高く維持できること、またシステムの柔軟性が保てることがわかりました」と森氏は振り返った。
なお、情報基盤チームは維持管理フェーズとなった現在も、当初のポリシーを堅持し、データベースの集中管理を行っている。経営統合段階で作った概念データモデルの骨格部分はこの10年、ビジネス環境が大きく変わる中でも崩れていないことは注目に値するだろう。
(まとめ:柏崎吉一)
データ分析の第一人者が語る
普通の企業における専門家や専門組織のやりがいと苦労

大阪ガス株式会社
情報通信部ビジネスアナリシスセンター
所長
河本 薫 氏
「見つける」「解く」「使わせる」――データ分析を課題解決に役立てる転機となったガス機器の修理携行部品予測システム
大阪ガスの情報通信部に所属するビジネスアナリシスセンター(BAC)は統計処理や分析の専門家9名で構成される組織だ。ただ、分析結果のレポート化のみならず、営業・マーケティング支援、工場での品質管理、さらに財務や人事部門を含むビジネス課題の解決に直結するコンサルティングやシステム開発支援すなわちソリューションを全社に提供していることが特徴だ。
BACが誕生したのはいまから約15年前だ。ただ当初は統計解析などを駆使した分析レポートを関係部署に持ち込んでも「そんな分析結果を聞くまでもなく分かっていた」「それで結局、会社の何の役に立つのか」と門前払いの連続。データを収集、クレンジングし、統計解析処理を行うのみではせいぜい計算が得意な便利屋、専門家と見なされるのが関の山であり、具体的なビジネス貢献を求められていた。
BACにとって転機となった事例のひとつが、ガス機器修理業務の効率化だ。「給湯器のお湯が出ない」といった利用者からの連絡を受けると同社のメンテナンス担当者は客先に向かい、点検、故障診断を行う。ところが、交換部品をその場に持ち合わせていないと後日再訪問が必要だ。給湯器の復旧遅れによる顧客の満足度低下の一因になっていた。メンテナンス担当者との何気ない一言でその実情を知ったBACは、過去10年分400万件のデータを分析。ガス機器の型番や使用頻度、症状によって交換部品に傾向があることを明らかにした。この分析結果をもとに「修理携行部品予測システム」の開発を上層部に提案。メンテナンス担当者が携行する優先順位の高い部品5つをリストアップし、それらの在庫状況を可視化する仕組みを作った。事前にリストをチェックすることで、訪問当日の修理完了率は大きく改善した。経験の少ない新人担当者も対応できるようになり、顧客満足度も向上させられた。出動回数も削減され、業務は効率化された。
BACではこうした事例を積み重ね、やがて社内から困り事が見つかったときの相談先として認められていった。現在では、営業や製造部門などのビジネスパートナーとして、ソリューション提供に対価を得る独立採算制で業務を進める。また子会社であるオージス総研と連携し、データの管理、整合性維持といったデータ基盤の整備を行うDUSHセンターも運営している。オージス総研ではBACのノウハウを生かしてコンサルティングサービスなど外販にも力を注ぐ。
河本氏は、データ分析部門が社内でその存在感を高めるには、解く力(分析力)だけでなく、社内のビジネス課題を見つける力(問題解決力)、分析結果を使わせる力、という3つすべてが重要だと指摘した。先述の「修理携行部品予測システム」の開発も、メンテナンス部門担当者の何気ない一言できっかけをつかんだ。手元にあるデータを使って試行版を作り、100人のメンテナンス担当者に利用してもらえるように、日々の作業導線にシステムを組み込んだ。現場に使い勝手のよさを実感してもらい、定着させるまで約2年半を費やした。
前述した3つの力を併せ持つフォワード型の自律的な人材が理想だが、「育て方に特効薬はなく、人材が育つ環境づくりが大切。まずは業務の現場をよく知ることです」と河本氏は強調した。
(まとめ:柏崎吉一)
食べたい寿司をタイムリーに
”スシロー流データ活用術”
株式会社あきんどスシロー
情報システム部
部長
田中 覚 氏

勘と経験をデータで裏付け、システムでオペレーションを支援
あきんどスシローは売上高約1,200億円、店舗数364、従業員数約35,000人の回転寿司チェーン店だ。いかにしておいしい寿司を、安く提供しているのか。大勢の来店客でにぎわう店舗の裏側では、リアルタイムに緻密なデータ分析が行われていた。
田中氏によれば、商品原価のおよそ5割は食材費で占められているという。高い原価率を維持するためには食材をムダなく使い切る必要がある。スタッフの効率的なシフト配置も重要だ。日々のオペレーションの中でデータを集め、その分析結果に基づいて経営資源の最適配分に磨きをかけている。
データの収集には、各席に設置された注文用のタッチパネルや、寿司皿の底面に取り付けられたICタグを用いている。お客様が来店されてからお帰りになるまでの間、どの席で、いつ何を注文したのか、レーンにはいつどんな商品を流したのかを、などを把握している。全店から集まる商品の売上データは年間10億件以上、タッチパネルの操作履歴データは年間40億件を超える。これらのビッグデータを利用して店舗オペレーションの改善や商品開発などを行っている。
全店のデータはETLツールを用いて、クラウド上にあるDWHに蓄積される仕組みだ。分析の用途に生じてデータマートを作っていくのに、CPU、メモリ、分析技術を自由に選択できるクラウドが適当と考えた。情報の可視化にはMotionBoard、QlikViewなどのBIツールを活用している。
「回転寿司総合管理システム」が店舗のオペレーションを支援している。このシステムは、お客様の食べ方をモデル化し、どのレーンに、いつどの商品どれくらい流せばよいのかを予測する。同社では、レーンに流している寿司の鮮度を保つため古くなった寿司は自動的に廃棄しているという。品切れや売れ残りを発生させないちょうどよい食材の準備するため、仕込みや発注にもデータを活用している。最近では、テイクアウトのシステムを開発し、製造キャパシティの管理や出来上がり時間の予測も行っている。
田中氏は、「データを活用するためのポイントは、まず、クラウドのような自由度の高い環境にデータを蓄え、分析の結果は現場ですぐ使えるレベルに加工する。様々なデータを組み合せれば新たな価値が生まれ、様々な予測やオペレーション改善につなげられます」と語った。
(まとめ:大倉愛子)
情報系システムアーキテクチャ策定の
ベストプラクティス
株式会社みずほ銀行
IT・システム統括第二部
藤本 真紀子 氏
業務タイプのパターン化基準に、データ要件と非機能要件を組み合わせる
2013年7月、旧みずほ銀行とみずほコーポレート銀行が合併し、グローバルを視野に入れた総合金融グループ、みずほ銀行が新たに立ち上がった。同時に、旧2行および、みずほ信託銀行のシステムと業務を統合、最適化するプロジェクトが始動している。一日のピーク取引数270万件のトランザクションを支える勘定系システムは、SOAベースで再構築、統合される。情報系システムについても各行、信託個別ではなく、全体最適の始点から整理統合が行われる。この本格的なプロジェクト開始に先立って、次期情報系システムにおける標準アーキテクチャを確立するアプローチの方法論に本講演では焦点が当てられた。
旧行では従来、各業務部門から上がる個々のシステム要件それぞれについてIT部門が個別にシステムデザインを行うアプローチを採用してきた。しかし、統合後に数百~数千規模の業務アプリが見込まれる情報系システムに、従来アプローチを適用し続ければ収拾が付かなくなる。検討の末に「システム要件を集約した上でパターン化し、同じくパターン化したアーキテクチャモデルにマッピングする方法に辿りついた」(藤本氏)した。これまでにない革新的なアプローチだったが、藤本氏はアーキテクチャの刷新は同行が進化を遂げる上での千載一遇のチャンスと捉えていた。
アプローチの方法論は3つのステップからなる。(1)各要件の組み合わせからなる汎用的な業務タイプの識別、(2)業務タイプに適する論理モデルの定義、(3)各層に適するテクノロジー候補の選定だ。ステップ1における業務タイプは、融資審査業務などの「高鮮度データを扱うトランザクション処理」、収益管理業務などの「日次の管理系業務アプリケーション処理」、信用リスク業務などの「週次・月次での分析業務アプリケーション処理」といった29種類に集約された。業務タイプをパターン化する基準には、データ要件(処理形態、データの量、鮮度、保存期間、粒度)および、非機能要件(利用時間、レスポンス、同時実行数、可用性、セキュリティ)が選ばれた。
DWHとデータマート(以下、DM)の役割も再定義した。DWHは勘定系で発生したデータを正規化して格納する。そこから業務横断的に利用される共通データマート(DM)、および目的別DMを作る形にした。これらをマッピングし、各業務タイプに適する論理配置モデルを策定する。各層に適するテクノロジー候補には、汎用DBMS、トランザクション特化型アプライアンス、分析特化型アプライアンス、超並列DBなどが挙がった。
今後の課題は、データ配置・実装のガバナンスを利かせることだ。データのトレーサビリティを向上させるための垂直ガバナンスはIT部門が推進する。機能やデータの乱立を防ぐ水平ガバナンスは業務部門が主導する。IT部門と業務部門の協業体制を検討中だ。ただし今回のアプローチにより、ガバナンス推進における基本方針は策定できた。アーキテクチャの決定基準の明確化、新規業務アプリ開発時に再利用できる手法の獲得、という目的も達成した。次期情報系システムの再開発プロジェクトはこれから本格化を迎えようとしている。「何を作るかが最終的なゴールではなく、何を実現するのかがより重要です」と藤本氏は結んだ。
(まとめ:柏崎吉一)
顧客満足を生み出し、業績貢献する仮説思考に基づくDBマーケティング

オイシックス株式会社
システム本部
本部長
山下 寛人 氏
「仮説思考」でデータを活用し、経営課題の解決精度を高める
安全で新鮮な食品の生産者と消費者を結ぶECサイトと宅配事業を柱に2000年に創業したオイシックス。「つくった人が自分の子供に食べさせることができる」というコンセプトに基づく厳しい商品基準をクリアした食材だけを取り扱う。契約農家は全国で約1000軒、2010年からはリアル店舗も展開し、取扱品目は現在3,300点以上にのぼる。野菜は自社で品質管理し、オイシックス物流センター (神奈川県海老名市)から小売店などに配送している。
同社は、創業初期からデータベースマーケティングに取り組み、未購入→リピート→定期購入と、顧客の属性や利用の段階に応じて訴求する商材を変える戦略を採ってきた。例えば、未購入者にはまず「おためしセット」として人気の高い食材だけを詰め合わせて届け、よさを知ってもらう。その後、定期購入へ誘導していく。
山下氏は、「当社の社長がマッキンゼー出身であることから、コンサルティングで用いられる仮説思考を全社的に取り入れています。問題を分解するイシューアナリシスではもれなく仮説を抽出し、強い仮説・インパクトの大きい仮説を選び出します。その中から有効性の高いものを絞り込んで検証しています」と解説した。
仮説検証の基盤となる情報システムは主に、商品管理、ECサイト、販売管理、在庫管理、出荷、会計などで構成され、各業務システムのDBは統合されている。受注集計の際には、SQLのwhere句を使って特定条件に合致するレコードを取り出せる自社開発のWebアプリを使用する。システム構築と運用、データ抽出はシステム本部が担当し、月間350件ほどのデータ抽出を実施している。DBの管理は、EC事業本部に在籍する分析に強いメンバーが、ユーザー部門の視点で行っている。経営企画ではそれらのデータをもとに、全社の予算、着地予測の策定、予実管理などを進めている。
前述のようなマーケティングを行う際には複雑なデータをDBから抽出する必要がある。ミスを防ぐ対策の一つとして、データ抽出依頼書やチェックリストが活用されている。さらに、抽出したデータが条件に合致しているかを調べる抜き取り検査や、2名の担当者によるダブルチェックも行っているという。
分析データの活用成果も着実に出ている。全社の売上・利益における予測値と確定値のズレは原因を分析することで精度を高めている。中でも需要予測は、鮮度が問われる野菜などの商材の仕入れで重用されている。また、定期購入を行う会員には毎週共通の基本セットが届くが、不要なものが届かないように解約率などの数値を見ながら中身をパーソナライズ化している。レコメンデーションの基本ロジックはデータを活用してほぼ完成の域に達している。
今後は、経営管理プラットフォームDomoの展開・活用、DBの分散化、クラウド移行を計画している。仮説思考を基本に据えながら、Rを用いた統計解析の手法にも注目するなど、さらに踏み込んだデータ活用が全社で進められる見通しだ。
(まとめ:大倉愛子)
ビッグデータ時代のBIシステム構築
開発標準化の取組みと活用事例について

カゴメ株式会社
経営企画本部
情報システム部
倉澤 紘己 氏
日々の業務や経営判断に欠かせないBIシステムを情報システム部門が集中制御
トマトジュース・野菜生活などの飲料をはじめ、カゴメ株式会社では幅広い食品の開発・販売を国内からアジア、ヨーロッパなど海外市場へ拡大を進めている。倉澤氏は、「年々業務が複雑・高度化し、様々な部門・役割で意思決定の重要性が高まっている。データ及びBIシステム活用の機会は今後一層拡大していく」と述べた。
同社のBIシステムが誕生したのは、1990年代である。汎用機から簡易プログラムを用いて必要なCSVファイルを抽出し、手元のExcelでデータを表示・加工する仕組みだった(同社BIシステムの第0期)。2000年から2001年にかけて同社のBIシステムは変貌を遂げる。業務システムをWindowsでオープン化したことにともない、BIシステムも刷新した(同第1期)。業務システムのRDBから抽出したデータを用いてSSAS(SQL Server Analysis Services)でキューブを生成し、クライアントPCのExcel 上でピボットテーブル化して、レポートとして閲覧する仕組みだ。現在もこの第1期のBIシステムが基本形となっている。営業担当者は出社すると、BIシステムで得意先の売上実績の推移を確認するなど、日々の業務に欠かせない役割を担っている。
第2期(2002年〜2012年)は、 BIシステムの拡大期だ。取り扱うデータや利用シーンの肥大化に伴い、課題も生じた。ユーザーの要望により、続々とDWHシステムは増え続け、システムドキュメントの改廃などが追い付かなくなった。また、データの粒度を月次から週次に詳細化するなど、データ量は増大しレスポンスは悪化した。また、盛り込む情報が増加したことでBIレポートの見やすさが犠牲になり、データの読解に時間を要するようになったユーザーが作成するExcelのBIレポート問題となった。Excelであるがゆえに、簡単にコピーが行われ亜種が氾濫した。誰がどんなデータを活用しているか情報システム部門から見えなくなり、ユーザーへの支援が希薄となった。
これらの課題解決に乗り出したのが、第3期(2013年〜)である。レスポンスの悪化に対しては、ハードウェアおよびRDBMSのバージョンアップとDWHにおけるデータ構造および開発手法の見直しによって大幅な高速化に成功した。視認性が低下していたUIは、グラフィカルなダッシュボードに更改して改善した。一連の業務改革では、情報システム部門が各業務部門と連携し、全社的な成果指標(KPI)の設定など情報システムの構築だけにとらわれない、幅広い領域で支援を行った。
システムの機能強化・維持管理では、DWHの構成情報の一元化に加え、一元化された情報が陳腐化しないための、中央制御可能な管理システムと業務ルールを構築した。
Excelから作成されるBIレポート自体の一元管理もユーザーと連携し、掲示板システムなどで一元管理を進めている。BIレポートの利用ログの取得と利用頻度に応じた増強・改廃などが課題であり、強化していく予定である
今後は、中央制御型のBIシステムへの刷新を、物流・生産・会計など領域を拡大していく方向である。最後に倉澤氏は、「業務改革コンサルタントとして業務に踏み込み、最適な活用方法を提案したいと考えている。また、データ量増大や活用高度化に備えて、IT基盤強化とシステム開発の標準化を進めていく」とまとめた。
(まとめ:大倉愛子)
